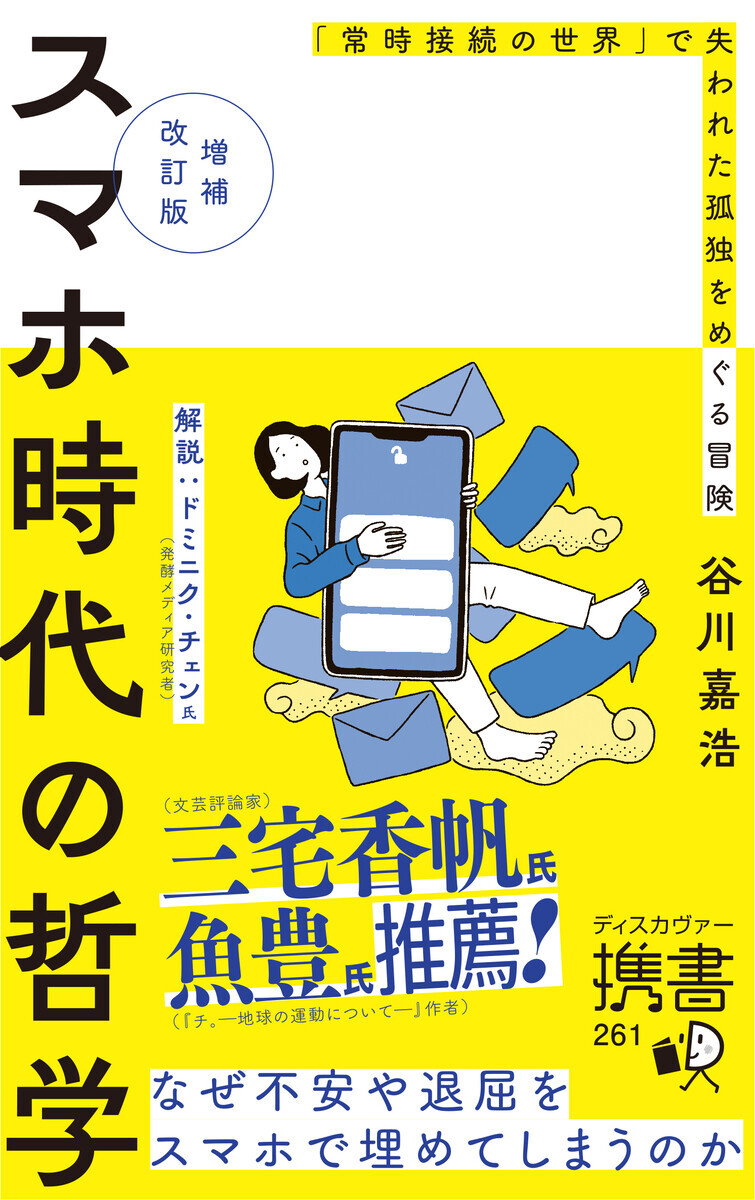谷川嘉浩氏の『スマホ時代の哲学』を読みました。副題に『「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険』とある通り、これは私たちの時間と関心をどんどん奪っていくアテンション・エコノミーが猖獗を極める現代において、私たちがいまとこれからをどう生きていけばいいのかを、さまざまな哲学者の思索を紹介しながら考えてみようという本です。
現代の私たちは、ネットに常時接続されているスマートフォンやパソコンなどのデバイスを片時も手放さず(手放せず)、つねにそこからのアテンション(注意喚起)と、それによる意識の分散に苛まされています。いや、苛まされているという自覚が必ずしもあるわけではなく、多くの場合、そうやって分散させられている自覚がないどころか、むしろそれが快感だったりします。こうして、街を歩けば私を含めて誰もが“低頭族*1”になっているわけです。
私がこうした意識の分散について、それが問題だと気づきはじめたのは2019年ごろでした。それから縷々考えたことをこのブログに書き連ねてきましたが、いま当時からの文章を振り返ってみると、アテンション・エコノミーから自分を引き剥がすのに相当苦労してきたことがわかります。いや、いまもまだ完全に引き剥がすことはできていませんし、また暮らしや仕事とネットがここまで密接に関係し合っている現在では、完全に引き剥がすことはもはや不可能だとも感じています。
それでも、SNSから降り、アフェリエイトをやめ、スマートフォンやパソコンの通知機能を可能な限り切り、eコマースからの買い物をできるだけ控えるなど、アテンション・エコノミーから自分を解放するための試み、言い換えれば「常時接続の世界」から距離を置く試みをいろいろと続けてきました。ようやく現在、この問題を意識し始めてから実に6年以上もの時間を費やして、毒が抜けかかってきたかなという感じです。
とはいえ、谷川嘉浩氏はこの本で、私のようないわば「断捨離」的なやりかたについてはかなり批判的に捉えられています。そうした一刀両断的で短絡的な思考に陥るのではなく、生きにくいことにまつわる「難しさ」や「モヤモヤ」や「消化しきれなさ」をある程度抱えつつも前に進むようなスタンス(ネガティブ・ケイパビリティ)が大切なのではないかと。そのために哲学という「道具」があるんだよ、というわけです。
たしかにそうだと思います。ただ、口幅ったいことを申せば、それは谷川氏が1990年のお生まれ、つまりデジタルネイティブと称される世代の方だからではないかなとも思いました*2。私はそれよりもかなり前に生まれた人間なので、ネットはもちろん、コンピュータ(パソコン)すら存在していなかった頃の暮らしを、身体がかすかに覚えています。
なおかつ、そこからパソコンが登場し、ネットにつながり、スマートフォンが普及していく世界の変容をずっと驚嘆とともに体験し続けてきました。その意味では「常時接続の世界」から距離を置こうとする試みも、いくぶんかは、やりやすいのかもしれません。TwitterやFacebookやInstagramやTikTokがなくてもそれまでと同じ暮らしが待っていることを、身体の記憶を根拠に信じることができるから。
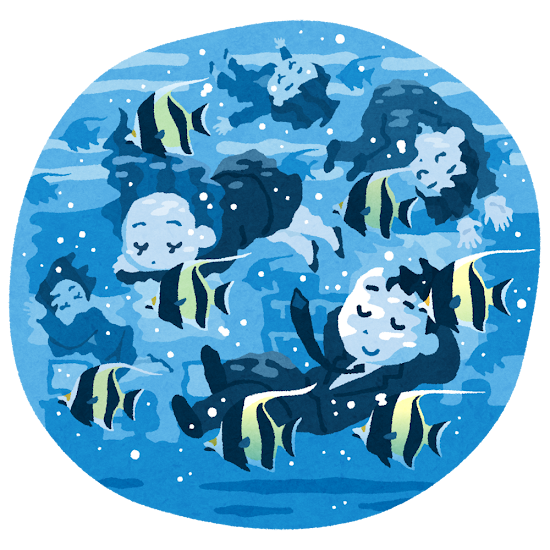
https://www.irasutoya.com/2016/04/blog-post_119.html
余談ですが、さいきん韓国語を学びはじめて、この言語に関するネット上の情報の多さに驚きました。英語や中国語も同じようなものですけど、学び方指南から「上達法」から小ネタやtipsなどの文章が膨大にあり、動画サイトにもたくさんの、しかもとても良くできた無料のコンテンツがあふれています。
それで、かつて自分が何十年も前に中国語を学びはじめた頃のことを思い出しました。当時はインターネットの黎明期で、動画サイトはもちろん、ブログもSNSなどもほとんど存在していませんでした。学習のための情報やコンテンツは現代とは比べ物にならないほど貧弱で少なかったですが、そのぶん「意識の分散」も少なかった。自分なりに工夫しながら学習することができましたし、なんなら現代よりもよほど集中して学べていたのかもしれません。
プログラマーで実業家の清水亮氏が『Wireless Wire News』に書かれていたのですが、氏は文章を書くとき、ネットに接続されておらずAIの助けも借りられない「Pomera(ポメラ)」を使っているそうです。失礼ながら、かねてからAIに関する氏の文章を読んで、なんだかマウント取りばかりしている方だなあと思っていた(ごめんなさい)ので、意外でした。
これを言うと年寄りがまたぞろ「ラッダイト運動」かよ、と揶揄されそうですけど、なにかに集中して取り組もうとするときは、ネットへの常時接続から自分を切り離したほうがよいのかもしれません。生成AIについても、私はこの一年ほどいろいろなサービスを(課金もして)使ってみましたが、少なくとも文章を書くことに関しては使わないと決めました。清水氏はこうおっしゃっています。
今やPomeraと静かに向かい合っている時間だけが、AIから解放される時間だ。
そうでない場所では、耐えずAIが原稿に提案や修正といったチャチャを入れてくる。
最初は面白かったし、それで楽ができると思ったこともあるが、もはやうんざりだ。
そうしたAI生成の文章はあくまでもAIの文章であり、僕の書きたいこととは程遠いのだ。
ごく稀に、それが僕の書きたいことを先取りしているかのように見えることもあるが、それこそが錯覚だ。
常時接続の世界は、とにかく騒がしい。そんな喧騒からそっと離れて、孤独な環境にこもることが、死活的に必要なのです。
*1:中国語で、スマートフォンなどの電子機器に依存して常に下を向いている人々を指す言葉です。
 電気通信事業者協会のポスターから
電気通信事業者協会のポスターから
*2:とはいえ、この本には「注意の分散に抵抗し、孤独になれる趣味を持て」といったような至言がたくさん。孤独の意味についても、新たな目を開かされました。おすすめです。